
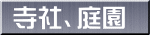





平沢寺の寺域
創建当時の平沢寺の敷地は現在の平沢寺の寺域をはるかに凌ぐ面積で関東でも有数の大寺院でした、その築造に携わった畠山重忠は鎌倉時代初期の頃に鎌倉三大寺院の一つに数えられていた「永福寺」の奉公人を勤めていた関係で平沢寺も浄土庭園を有するなど永福寺の様式が取り入れられていました。

(現在の平沢寺)
平沢寺参道前の鎌倉街道


(平沢寺参道前の鎌倉街道筋)
平沢寺の参道は鎌倉街道上道に通じていました、この鎌倉街道沿いを南東方向へ進むと畠山重忠の居館であった菅谷館、もしくは木曽義仲が生誕した大蔵館へと通じています。
出城坊


平沢寺の鎌倉街道筋に接した参道口付近には小山が在り警備施設である出城坊が置かれていました。
平沢寺参道


鎌倉街道筋から平沢寺の中心の伽藍に向かって一直線に参道が延びて両脇には在家の家々が建ち並んでいました。
平沢寺の中心部


平沢寺中心部に入ると「薬師の池」があります、中心部は奥州平泉の毛越寺、平等院と同様に極楽浄土を表した浄土庭園が造られていました。
方三間堂


(方三間阿弥陀堂跡)
薬師の池の背後に宝形造りの方三間阿弥陀堂がありその更に裏手に2棟の伽藍が建てられています、それら方三間堂を含む3棟の伽藍は薬師の池からの景観を考慮して斜めに徐々に高く配置されています。
赤井の井戸


伽藍中心部から南へ進むと「赤井の井戸」が在ります、当時平沢地域は水利の大変悪い所でこの寺域に掘られた赤井の井戸を共同井戸としていました。
大日山


赤井の井戸の向かい側の山は「大日山」と呼ばれ真言系の坊である大日堂が建てられていたと考えられます。
禅座屋敷跡


大日山の南側の背後には禅座屋敷が設けられ僧侶達が座禅を組む道場と成っていました。
比企尼屋敷


中心伽藍から反対方向の北側へ向かうと源頼朝の乳母であった比企尼御前の屋敷が在りました、比企尼の甥の比企能員は鎌倉幕府の有力御家人となっていましたが鎌倉幕府初代執権である北条時政に謀反を企て時政に殺害されています、その能員は同比企郡の松山市「正法寺」参道前に居を構えていました。
「吾妻鏡」によれば1187年(文治2年)と翌年の文治3年には頼朝と北条政子の夫妻が此処「比企尼屋敷」を訪ねて宴会を模様したとあります。
獄之坊


比企尼屋敷の東側には獄之坊が置かれていました。






















